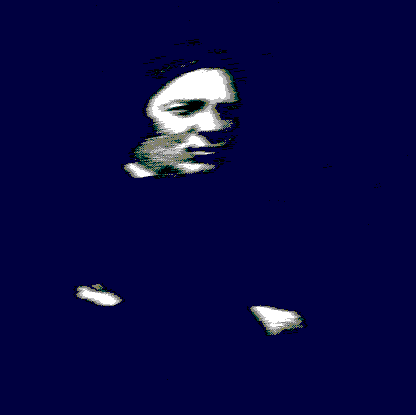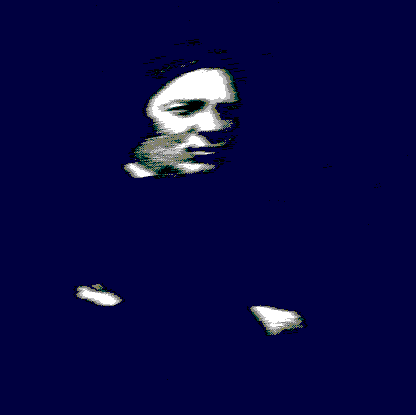【 本文 】
シューマンを代表する作品として知られているものの中に『子供の情景』作品15がある。これは13の小曲で構成されている。第7曲の標題「トロイメライ Traeumerei 」は慣用的に夢と訳されている。より辞書的に訳せば夢想だ(夢はトラオム Traum)。夢も夢想もシューマンの内面を解く言葉だ。
夢や夢想、あるいは幻想という言葉は当時の思潮=ロマン主義運動と深く関係している。暴力的にまとめてしまえば、ロマン主義運動とは人間の内面の自由を芸術によって実現しようという運動だ。旧弊や束縛の多いこの現実世界とは別の自由な世界を精神内部に描くという一種のユートピアニズムだ。そのユートピアニズムは、文学では物語(特に童話)の形で表現された。そうした文学において、夢は「悟性による現実世界の認識を越える別の法則」として利用された(*1)。
ロマン主義の動きは、少年期から親しんだ多くの文学作品を通してシューマンの内面に移入されていった。また、シューマンは歌曲のテキストとしてロマン派詩人の詩を多く採用している。シューマンが影響を受けた文学者としては、ジャン=パウル、E・T・A・ホフマン、バイロン、ゲーテ、シラー、ハイネなどがあげられる(ロマン派ではないがシェイクスピアも重要だ)。ロマン派のティーク、シャミッソーの作品は歌劇や歌曲集のテキストとして採用された(*2)。
シューマンには『ダヴィッド同盟舞曲集』作品6というピアノ曲集がある。1834年に音楽評論のための雑誌音楽新時報を創刊した際、シューマンが作った空想上の団体がダヴィッド同盟だ。シューマンはこの雑誌に執筆する時、3つの筆名(ラロ先生、フロレスタン、オイゼビウス)を駆使し、それぞれの筆名に自分の人格のある部分を担当させて発言させた。フロレスタンとオイゼビウスのように、対照的な性格の人物を対比して描くという着想は、ジャン=パウルの小説『生意気盛り』にヒントを得たものだ。
『謝肉祭』作品9は22の小曲から構成されている(*3)。日本語では聖書の訳との関係でペリシテ人と訳されているフィリスティン Philistin は、ドイツの学生言葉では俗物を意味している。
シューマンが言う俗物とは音楽的俗物のことだ。このフィリスティンをダヴィッド同盟が討ちにゆく。だが、なぜダヴィッド同盟なのか? 旧約聖書に出てくる巨人ゴリアテに戦いを挑んだダヴィデの名に因んでいるからだ。ダヴィッド同盟が戦うのは音楽的俗物(フィリスティン)で、シューマンはこれを巨人ゴリアテにたとえた。
この終曲ではフィリスティンを意味する旋律として17世紀の民謡〈おじいさんの踊り〉が用いられた。この旋律は『蝶々』でも用いられた。(余談だが、この旋律はチャイコフスキーの『くるみ割り人形』第2幕でも用いられた。)
シューマンにとって重要だった作家はE・T・A・ホフマン、そしてなんといってもジャン=パウル・リヒターだった(*4)。 そのジャン=パウルの小説『生意気盛り』からの抜粋メモに基づいて作曲されたのが『蝶々』だと考えられている(*5)。この小説はヴィーナというマドンナをめぐる双子の兄弟ヴァルトとヴルトの物語だ。ヴァルトは法律を学んだ詩人、ヴルトはフルートを吹く音楽家だ。この双子の姿は、詩人となるか音楽家となるかで迷いながらも法律を学ばざるを得なかったシューマンの姿と重なる。
シューマンはこの小説の仮面舞踏会の場面をイメージの中心に置いて『蝶々』を作曲した。仮面舞踏会で情熱家ヴルトは夢想家ヴァルトになりすまし、ヴァルトのためにヴィーナに愛をささやく。やがて仮面舞踏会の終わりを告げる深夜の鐘が鳴る。ヴィーナとヴァルトを結びつけたヴルトはフルートを吹きながら去ってゆく。
ところで、この作品の終曲には小説からの抜粋がつけられていない。シューマン自身も何も語っていない。だが当初、作品の冒頭に『生意気盛り』の最後の部分(「通りから静かにきこえはじめたフルートの響きがやがて遠ざかってゆくのを、ヴァルトは夢中になって聴いていた。弟もまた去りゆくのだということに気がつかなかったのだ」)がモットーとして提示されていたことがわかっている(*6)。
シューマンは終曲でこのモットーを音楽化したとも考えられる。終結部直前で鐘が鳴るのが聴こえる(譜例1)。ヴルトの吹く笛の音が消えてゆく情景は、押さえている鍵盤を1つ1つ放してゆく和音の引き算で表現される(譜例2)。同様の和音の引き算=消えてゆく和音は『アベッグの名による変奏曲』作品1にも見られる。『アベッグ変奏曲』の場合、消えてゆく和音は架空の伯爵令嬢アベッグの綴り(ABEGG=イ・変ロ・ホ・ト・トの各音)を構成している。この消えてゆく和音について、前田昭雄氏は「音響を否定して、『詩』の響きが内へと滲み入る。ドイツ語で Er‐innerung は、『内面化』であってまた『想起』でもあると言うことが、これほど端的に観得される音現象は稀だろう…これは、音詩人シューマンの初期に特有な詩的観念的なタッチである…『ABEGG』は音であって、同時に詩的想念でもある」と述べている(*7) 。
シューマンは自分が創刊した新音楽時報という雑誌に、複数の筆名を使って評論を書いていた。特にフロレスタンとオイゼビウスはシューマン自身の性格の両極をそれぞれが担っている。フロレスタンは激情的で挑発的、心の内を激しく表現する闘士で熱血漢だ。オイゼビウスは瞑想的で物静か、情熱を内に秘めた詩人だ。フロレスタンとオイゼビウスは2人ともダヴィッド同盟の一員ということになっている。『ダヴィッド同盟舞曲集』の初版では、各曲にフロレスタンとオイゼビウスの振る舞いが物語風に記されていた…(ア)。 また、それぞれの曲がどちらの人物によって書かれたかを示す署名(フロレスタン Florestan のF、オイゼビウス Eusebius のE)が末尾あった…(イ)。しかし、第2版では(ア)(イ)ともに削除されている(*8)。
FとEの署名がない作品にも、この2つの性格が一貫して現れるのがシューマン作品の最大の特徴(魅力)であり、弱点でもある。FとEの均衡がとれ、構成上うまく処理されている場合には、限りなくシューマネスクな世界がくり広げられる。しかし、どの作品においてもこの2つの性格が延々と繰り返されるため、時として強迫的な単調さに彩られることさえある(*9)。
この対比が成功している作品の例としては、『アダージオとアレグロ』作品70が挙げられる。アダージオ(=ゆっくりした速度で)がE、アレグロ(=快速に)がFの性格を持っている。なお、作曲者によって指定された楽器編成はホルンとピアノだが、ホルンのかわりにヴァイオリンかチェロを用いてもよいことになっている。指定には入っていないが、木管のオーボエやクラリネットで演奏されることも決して珍しくはない。
シューマンには完成した交響曲が4つある。そのうち、第3番 変ホ長調が最も最後に書かれた作品だ。第4番の出版に先立つので第3番という番号がふられている。1850年に作曲され、出版はその翌年だ。全体は5楽章で編成されている。通称は『ライン』。(これはシューマンの命名ではない)
この交響曲の第4楽章はケルン大聖堂で行われた枢機卿叙任式を見たことがきっかけで書かれた。当初、荘厳な儀式を伴奏するようにという指示があった。しかし、この指示は標題的すぎるため、出版時に削除された(*10)。ただ、荘厳な Feierlich という部分だけが残された。バッハ風の書法と荘重な金管の息の長さはブルックナーの響きを先取りしている。この楽章からはチャイコフスキーも影響を受けたと言われる。
『ライン』の主要な調性は変ホ長調だ。変ホ長調はシューマンが特に好んだ調だ(いずれの作品も明るい色彩を持っている)。変ホ長調で書かれたベートーヴェンの交響曲第3番『英雄』を意識していたとも考えられる。
『英雄』は4楽章編成、変ホ長調 → ハ短調 → 変ホ長調 → 変ホ長調。第2楽章の〈葬送行進曲〉のみがハ短調(!)だ。一方、『ライン』の各楽章は変ホ長調 → ハ長調 → 変イ長調 → ハ短調 → 変ホ長調で書かれている。変ホ長調と、その平行調のハ短調で構成されている『英雄』ほどのストレートさはないが、関係の近い調でシンメトリカルにまとめられている(たとえば変イ長調は変ホ長調の下属調、ハ長調はハ短調の同名調というように)。
『ライン』の第4楽章は『英雄』の「葬送行進曲」と同様、変ホ長調交響曲の中のハ短調楽章だと改めて意識して聴いてみると、そこにベートーヴェンがイメージした英雄の葬列を照らす松明の輝きが見えはしないだろうか。ベートーヴェンという松明からの、深く、荘厳な照り返しが…。
シューマンは18歳の時に『英雄』を聴いて感激し、「自分もいつかこのような交響曲を書きたい」と思うようになったと伝えられる。22歳の時にはト短調交響曲『ツヴィッカウ』を書きはじめたが、これは未完だ。28歳の時、それまで知られていなかったシューベルトの交響曲を自ら発見して世に送り出した。僚友メンデルスゾーンの初演でこのハ長調交響曲『ザ・グレイト』を聴いたことが直接のきっかけとなって、再度シューマンは交響曲の作曲に取り組むこととなった。未完作ハ短調を経て、30歳の時に4楽章編成の変ロ長調交響曲を書いた。
交響曲作家としてのベートーヴェンの後継者はブラームスだと広く考えられている。この認識は不適切だ。もちろんブラームスもベートーヴェンの後継者の1人には違いないが、それよりも彼はシューマン直系の後継者だった。ブラームスはシューマンを師ではなく我が主と呼んでいたほど終生尊敬し続けた(*11)。
ドイツ=オーストリア系交響曲の流れは、ハイドン → モーツァルト → ベートーヴェンからブラームスに直結するのではなく、ベートーヴェン → シューベルト → シューマン(とメンデルスゾーン)を経てブラームスに至るのだということを改めて確認する必要があるだろう。 (終)
|